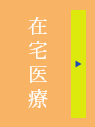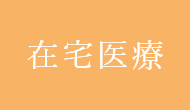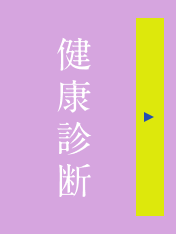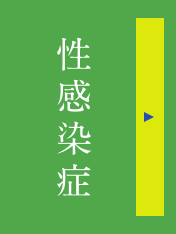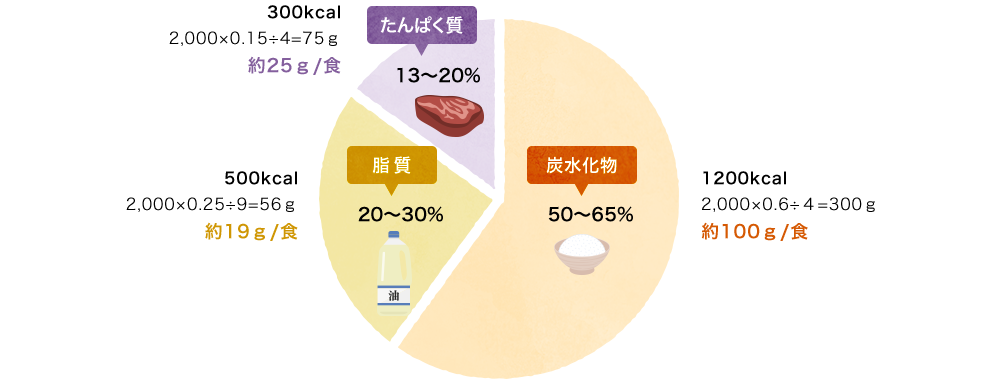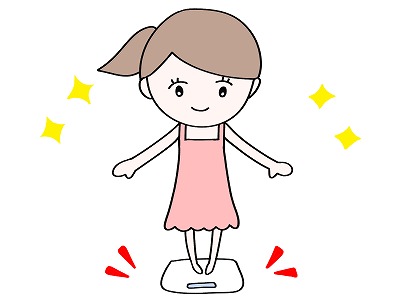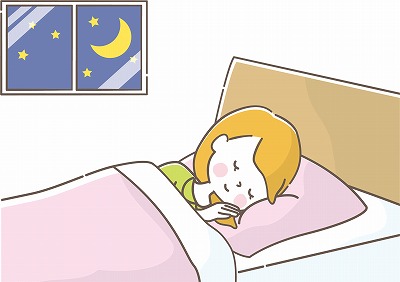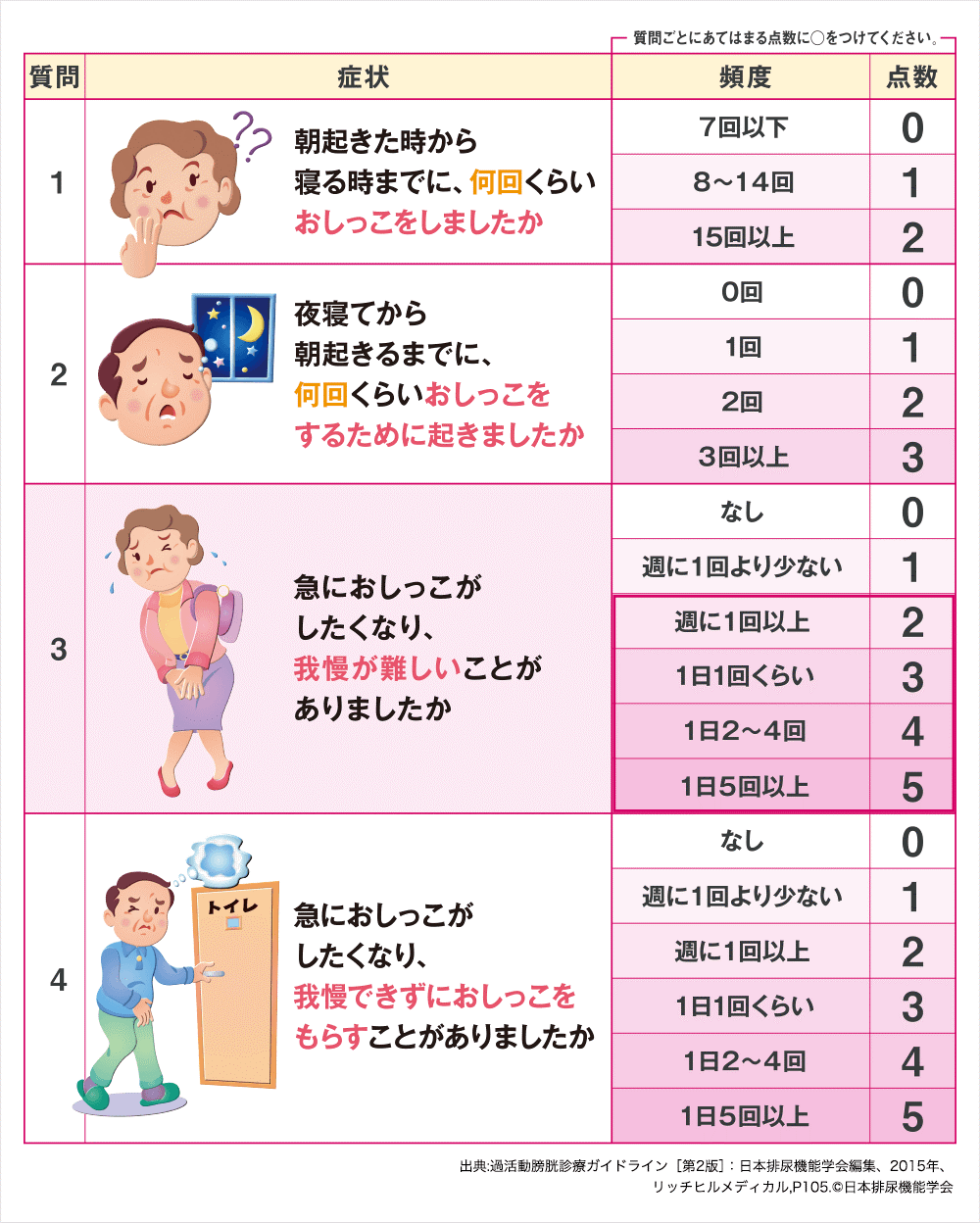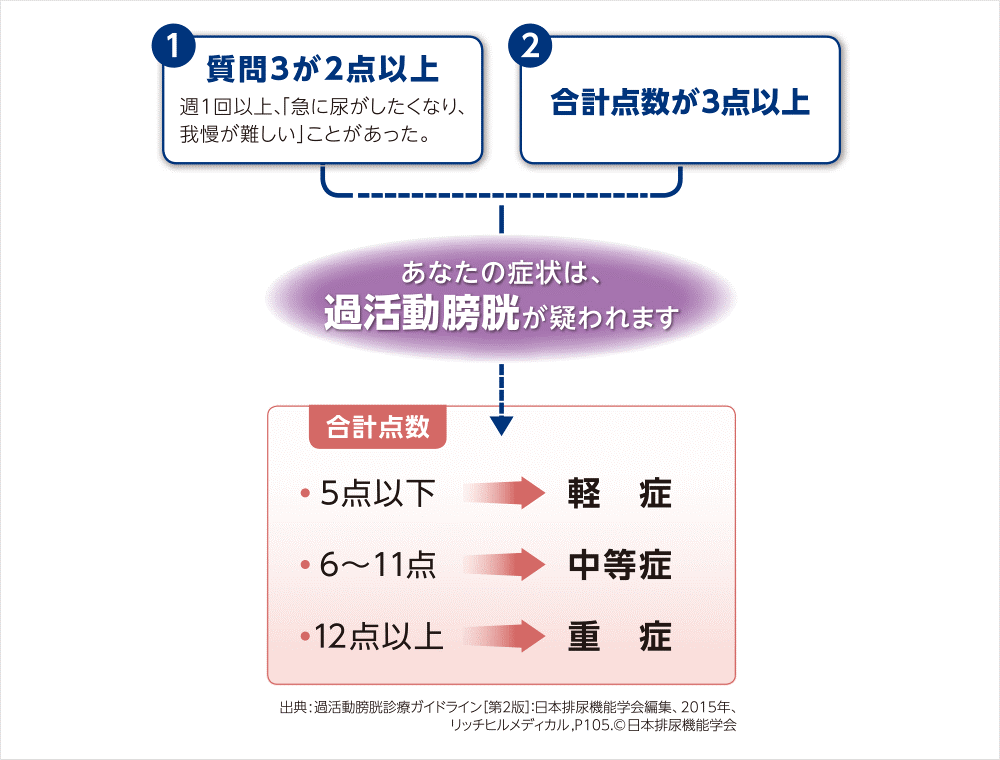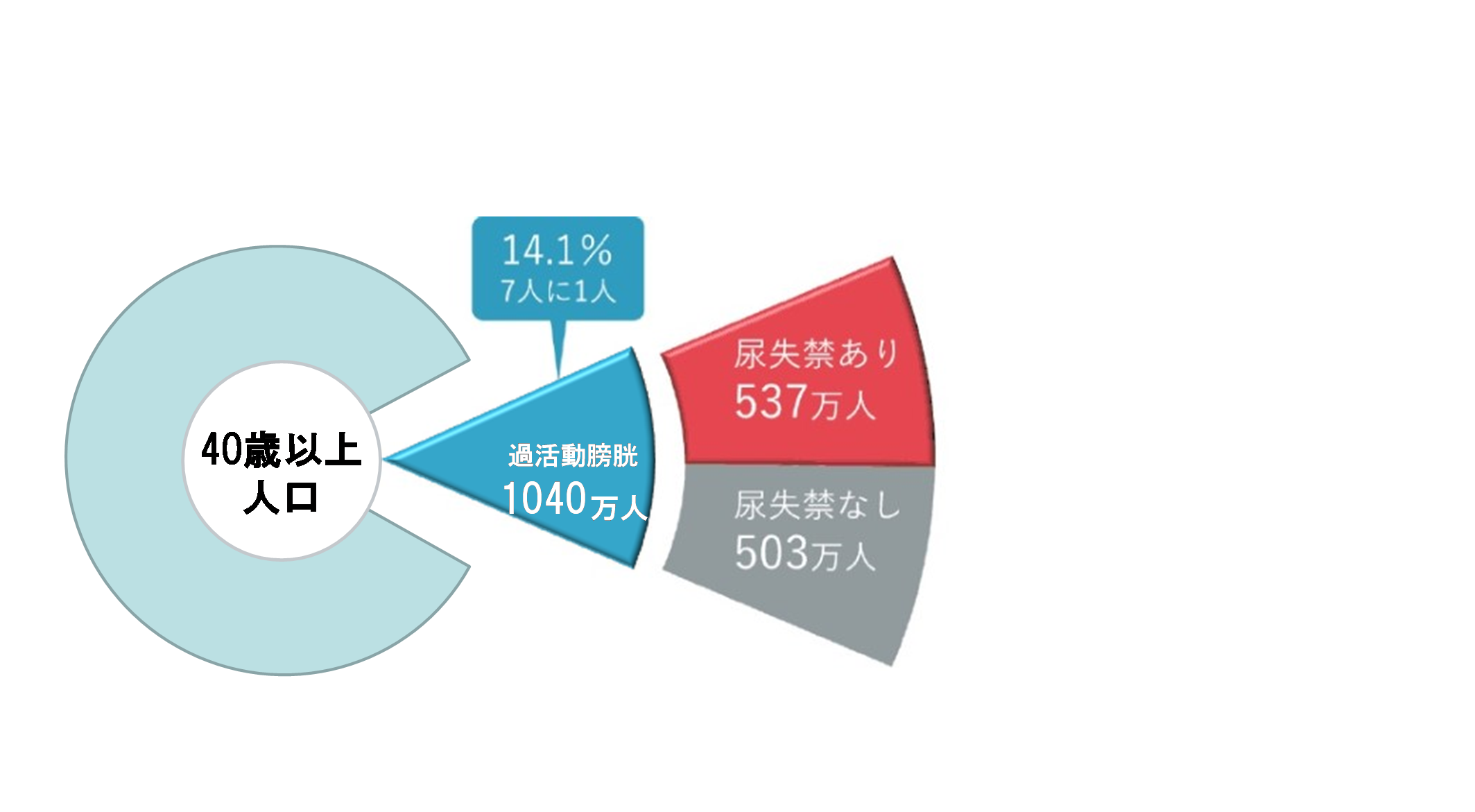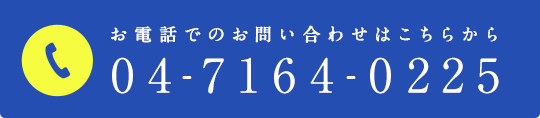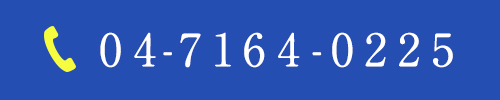膿、強い排尿時痛とおりものの異常:淋菌感染症/大林広輝
2024.06.28更新
クラミジア感染症に続き、淋菌感染症を
より現場に近いリアルな視点で解説していきます。
男性は膿の排出や強い排尿時痛、
女性はおりものの異常や下腹部の痛みがある場合、
原因の一つとして淋菌感染症が考えられます。
クラミジア感染症のコラムを読んでいただいた方はお気づきだと思いますが、
症状が似ている部分があります。
男性の排尿時痛や女性のおりものの異常はどちらの感染症でも認めるため、
症状だけで判断するのは困難となります。
しかしクラミジアと違いを認める部分もあります。
基本情報や対処法とともに解説していきます。
淋菌感染症とは
淋菌感染症は、性的接触によって人から人へと感染します。
感染経路としては、膣性交だけでなく、
肛門性交、オーラルセックスからも感染のリスクがあります。
コンドームを使わない場合は1回の性行為で30~50%の確率で感染するといわれています。
喉に感染することや生殖器から出る分泌物に触れた手で目を触ることによって、
目に淋菌が感染することはクラミジアと同様です。
男性の性感染症の45%,女性の性感染症の63%がクラミジア感染症,
男性の性感染症の30%,女性の7%が淋菌感染症であったという報告があります。
感染数は男女ともにクラミジアと比べると淋菌は少なくなります。
特に女性で感染数の差は大きくなります。
症状の現れ方
淋菌感染症はクラミジアと同じ様に感染しても、
女性では初期段階では症状がほとんど現れません。
男性は初期の段階から膿の排出や強い排尿時痛を認めるため、
症状が軽度であるクラミジアとの違いになります。
女性の場合は、おりものが多くなる、においがいつもと違うといった症状が出てきます。
おりものの色がクラミジアより黄色や黄緑色になりやすく、下腹部の痛みが多いところが異なる点です。
ただし、男女ともに淋菌感染症であっても症状が軽度であったり、自覚しないことがありますので、
必ず検査でチェックするようにしてください。
診断と治療
診断は
男性であれば尿検査、
女性であれば膣から拭き取り検体による検査で行われます。
男女ともに喉の感染はうがい液を採取して検査します。
治療は点滴(セフトリアキソン)や筋肉注射(スペクチノマイシン)によって
ほぼ100%完治します。
クラミジア感染症と同様に治療で重要なことは
感染が確認された場合、パートナーも検査を受け、必要であれば治療を受けることです。
パートナーが感染したままでは、自分が完治しても再度性行為をすることで感染することが考えられます。
淋菌感染を治療しないままでいると、男女ともに不妊症のリスクが高くなります。
予防策
淋菌感染を防ぐ最も有効な方法は、安全な性行為を行うことです。
コンドームの正しい使用が感染リスクを大幅に減少させます。
また、定期的な性感染症の検査を受けることも予防につながります。
おまけ
男性の淋菌感染症では膿が出るということが、クラミジアと異なる点になりますので、
問診では膿の排出についてお聞きします。
ただし、「膿」についての理解が医療者と患者さんでは少し違う場合があります。
医療者は膿をどろっとした黄白色のものとして考えます。
もちろん我々と同じ膿を想定している患者さんも多いですが、
下着に白いものが付着していたから膿が出ていたと考える患者さんもいらっしゃいます。
クラミジア感染症の場合は透明なさらさらした液(漿液性)が出てきて、
それが下着に付着して乾燥すると下着に白い付着物がついたように見えます。
この白い付着物を膿と認識している患者さんが少なからず見受けられます。
医療者側も間違えないがないように、
どろっとした黄色い膿が尿道から直接出ているかをお聞きするようにしています。
みなさんも下着についた白い付着物だけを見て「膿」と判断しないように注意してください。
最近ではクラミジアと淋菌を同時に感染する方が増えています。
問診や症状だけで決めることは難しいため、必ず検査を受けるようにしてください。